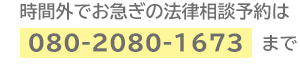相続・遺言
相続
相続とは、親族が亡くなった際に、その親族が所有していた財産(遺産)を特定の人が引き継ぐことをいいます。
亡くなった人を被相続人と呼び、遺産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続には、大きく分けて
「遺言相続」 と 「法定相続」 の2種類があります。
- 遺言相続(指定相続)
被相続人が生前に作成した「遺言」によって、遺産の分配方法が指定されている場合、原則としてその内容に従って遺産を承継します。
ただし、一定の法定相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されており、遺言によっても完全には奪うことができません。
- 法定相続
遺言が存在しない場合、民法の規定に従って相続が行われます。
この場合、法定相続人の範囲や相続分は、民法に基づいて定められます。
- 配偶者は常に相続人となる(配偶者相続権)。
- 子(直系卑属)がいれば、配偶者とともに相続人となる。
- 子がいない場合、親(直系尊属)が相続人となる。
- 子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人となる。
- 相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属する。
共同相続と遺産分割
法定相続において、
相続人が複数いる場合は 「共同相続」 となり、
相続人全員が遺産の一部ずつを共有する状態になります。
しかし、そのままでは遺産を個別に管理・処分することが難しいため、
具体的に誰が何を取得するのかを決める 「遺産分割手続き」 が必要になります。
遺産分割の方法には以下の3つがあります。
- 協議分割:相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるかを決定する。
- 調停分割:協議で合意できない場合、家庭裁判所の調停を利用して分割方法を決める。
- 審判分割:調停が成立しない場合、裁判所が審判で分割方法を決定する。
相続には、遺言の有無、相続人の範囲、遺産分割の方法など、
さまざまなルールが関係しており、
スムーズに進めるためには法律の知識や適切な手続きが必要となります。
遺言
「遺言」を、法律家は「ゆいごん」ではなく、「いごん」と読んでいます。
もちろん、一般には「ゆいごん」という表現で問題ありません。
さて、どんな時に、遺言を書いておく必要があるのでしょう。
たとえば、法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合、何もしなければ、当然、法定相続人のもとに財産が行くことになります。
また、法定相続人(たとえば、妻と子が二人)がいる場合であっても、「誰にどれだけ譲るのか」を何も決めなければ、法律で決められた通り、妻が二分の一、子がそれぞれ四分の一ずつとなります。これを変えたいなら、遺言が必要です。
土地や建物のように簡単に分割できないものを譲る場合も、遺言で例えば土地は妻、建物は子と指定することができます。
まとめると、「遺言」とは、遺言者の最終の意思を表したもので、これにより自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができるのです。
相続が、いわゆる"争族"になるのを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、
①「自筆証書遺言」
②「公正証書遺言」
③「秘密証書遺言」
の3種類があります。
遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になってしまいます。
たとえば、自筆証書遺言の場合、ワープロで打たれたものは無効となります。
3種類のうち、もっとも安全で確実なのは②「公正証書遺言」です。
「公正証書遺言」とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。作成時に公証人に対して、作成手数料を支払います。
「公証人」とは、実務経験を有する法律実務家の中から法務大臣が任命する公務員で、「公証役場」で執務しています。元裁判官や元検察官をイメージされればよいと思います。 「公証役場」は日本全国に300箇所ほどあります。利用しやすい場所を選べば良いでしょう。
「公正証書遺言」は、法律の専門家がチェックするので、無効なものになる心配がありません。また、紛失、偽造を防止できるのも、大きなメリットです。
作成された原本は、原則として20年間公証役場に保管されます。
20年間の期間が経過した後も、特別の事由により保管の必要がある場合は、その事由がある間であれば原本は保管されますし、実務の対応として、20年経過後も原本を保管しているのが通常です。
なお、令和2年7月より、法務局で自筆証書遺言保管制度が始まりました。
遺留分
Aさんには、妻と二人の子(BとC)があるが、Bには財産を相続させたくない。
そこで、妻とCだけに相続させる旨の遺言を作ったとします。
Aさんの死後、Bとしては何か権利主張できるでしょうか。
このようなケースでも、Bが一定の財産を「自分によこせ」と請求できることが原則として認められています。
その一定の取り分を「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
そして、この「自分によこせ」という請求を、「遺留分侵害額請求」といいます。
この仕組みは、なんだか理不尽な気もします。
しかし、次のように考えられているのです。
「財産の中には、家族の協力によって得られた物もあるはずだし、残された家族の生活を保護すべき場合もあるから、本人のまったくの自由を許すべきではない。だから、最低限の財産につき、家族は請求できる。」
とにかく、遺言の内容を一部覆してしまうものなので(遺言によっても、遺留分を奪うことができない)、注意が必要なところです。
なお、本人(被相続人)の意思を尊重する制度として「推定相続人の廃除(はいじょ)」という制度があります。被相続人に対して虐待、重大な侮辱その他著しい非行をした場合、被相続人の意思に基づき、その推定相続人から相続資格を奪う制度です。
さて、「遺留分侵害額請求」は、本人(被相続人)の自由を犠牲にする制度なので、法定相続人のうちでも重要なものに限定されています。
兄弟姉妹は、「法定相続人」にあたる場合であっても、「遺留分」は認められません。
「具体的にどのくらいの財産まで「遺留分」となるのか(侵害額請求できるのか)?」については、民法1042条に規定されています。
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額をうける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算出したその各自の相続分を乗じた割合とする。
先のケースでは、「法定相続人」は、配偶者(妻)と子(BとC)なので、「二号」に該当します。「被相続人」とはAのことで、その財産の二分の一が「遺留分」として請求される可能性ある財産となります。
他方、Bの相続分は四分の一です(配偶者と子が相続人の場合、配偶者が二分の一、子が二分の一。子どもが複数なら、それぞれはその数で割った割合。この場合、BとCの二人なので、二分の一をさらに2で割って、それぞれ四分の一ずつとなる)。
以上から、Bの遺留分は、全遺産の八分の一になります(二分の一×四分の一)。
遺留分侵害額請求権には期間制限があり、「遺留分権利者が、相続開始及び侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」、または、「相続開始の時から十年」で時効消滅します。
遺産分割
「遺産分割」とは、一言でいえば、亡くなった人の遺産を複数の相続人が分けることです。
遺言があれば、それに基づいて遺産が分けられます。遺言に指定された遺言執行者が遺言通りに分けられるようにします。
遺言がない場合、相続人の間で遺産をいかに分けるかを協議します。
法律は、法定相続人の相続分につき規定していますが、それに必ずしも縛られず、話し合いで決めることができます。
たとえば、相続人が妻と子である場合、法律の定める相続分はそれぞれ二分の一ずつです。しかし、残された妻の今後の生活もあるので、妻が遺産のすべてを相続するケースもあります。これは配偶者100%、子が0%という割合で遺産を分割したということで、相続放棄とは異なります。
相続人同士の人間関係が比較的良好で合意できる場合には、かなり柔軟に遺産分割を決定できます。実際には、各相続人の現在の生活状況や亡くなられた方との生前の関係などによって、法定相続分にとらわれない割合で定めることが一般的です。
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ成立しません。
よって、相続人のうち一人でも内容に同意しない者がある場合や協議できない相続人がいる場合には、調停等の裁判所の手続きを利用して解決することになります。
遺産分割「調停」では、調停委員2人が、申立人側と相手方側それぞれを順番に調停室に呼び、それぞれの言い分を聞きます。そのうえで妥協点を探して、それぞれに調停案を提示していきます。
「調停」で話がまとまらないと(調停不成立)、手続きは遺産分割「審判」に進みます。
「審判」とは、家庭裁判所が後見的な立場から、資料を検討して決める手続きです。
裁判官は、資料を客観的に精査して、断を下します。そこで、いかなる資料をいかに裁判官に示すかが大事になります。